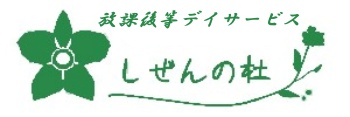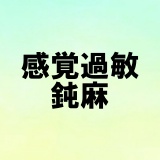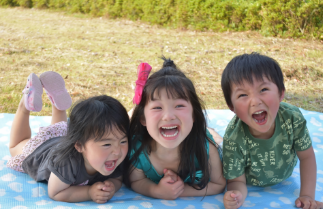感覚過敏・鈍麻について
感覚過敏・鈍麻は、発達障害にともないやすい感覚の特性です。
感覚に関して敏感に反応し、生活の中で不便が出てくることを感覚過敏といいます。
過敏の程度もありますが、症状も違うため、聴覚過敏、触覚過敏、視覚過敏など5感に関するものが過敏に反応するものの事を言います。
反対に、感覚が鈍感で不便が見られることを感覚鈍麻と言います。
自閉症スペクトラム障害(ASD)がある方などは、抑えきれない苦痛やストレス増大にもつながるため注意してみていく必要があります。
苦手なものは無理にさせるのではなく、苦手な部分をうまく対処できる方法や工夫を行い、ストレス緩和を図りながら生活しやすい状況を作っていくことが必要です。
自己肯定感を育み、楽しいと感じてもらいながら関わっていくことが大事です。
療育方法

感覚過敏・鈍麻の子どもたちの療育では、まずはどの5感(視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚)に問題があるのかで対処方法が変わってきます。
まずは原因を取り除くことが大事になるため、普段の生活面で離れたり、避けることも必要になってきます。
脳に入ってくるいろいろな感覚を、うまく整理したりまとめたりする感覚統合を練習するのも良いでしょう。

感覚過敏や感覚鈍麻を自力で治すことは困難です。
そのため無理に嫌がるものを食べさせたり、触れさたり何度も見せたりしても逆効果になることが見られます。
どのように対処しないといけないかは、五感の感覚にどこにアプローチをかけ接するかが基本になってきます。
理解を深め焦らず接することが大事です。
視覚過敏の対処法はどうすればいいですか?
テレビやスマートフォンの画面は光が強く感じるときが多いため集中力が分散してしまうことがあります。
また、日光や部屋の明かりがまぶしい時にはブルーライトカットメガネやサングラスを活用するといいといわれています。
聴覚過敏の対処法はどうすればいいですか?
耳栓やイヤーマフ(ヘッドホン)の活用がをされる方が多いですが、日常生活で外に出たときに車や電車が来る音なども聞こえないときもあるため、ノイズカットを全部行うと危険があります。
周囲の協力を促し、対応していくことが大事になってきます。
嗅覚過敏の対処法はどうすればいいですか?
現在は、感染症対策の理由でマスク着用する方が増えてきており、子どもらしいマスクもたくさんあります。
臭いにも好きなもの、落ち着くもの、嫌なものが分かれているため、落ち着く臭いはどんなものなのか理解し誘導していくことが大切です。
味覚過敏の対処法はどうすればいいですか?
好きなものは何なのか把握し、過敏な場合は薄味にしてみたり、苦手なものは食べないようにしましょう。
苦手を克服することに注目することではなく、好きなものができるように工夫して食べられるものを探していくことが大事でしょう。
ストレス緩和も行えてくるため、普段の生活で過ごしやすくなってくるでしょう。
触覚過敏の対処法はどうすればいいですか?
よくあるのは、普段の衣類に使っている素材が気になる子どもが多いと感じます。不快に感じない素材を探していき、縫い目が少ない物やタグの処理がしやすい物など探していくといいでしょう。